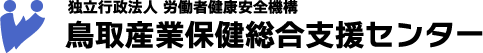所長のメッセージ
: 令和7年7月によせて
鳥取産業保健総合支援センター 所長 黒沢 洋一
◇
『「令和の米騒動」と「天才」』
◇
◇米の値段が高騰し、「令和の米騒動」という状況になっている。日本の米の年間消費量は、
およそ700万トン、世界で9番目の消費量である。ただ、一人当たりの年間消費量は、1962
年をピークに一貫して減少傾向にある。1962年118.3キロだったのが、2022年には50.9キロ
まで減少した。米の高騰により、消費者の米離れが進むことが懸念される。
◇米離れといえば、私の故郷、香川県、讃岐国は、元々コメ離れした地域といえよう。讃岐
国は瀬戸内式気候で降雨量が少なく、大きな川もないため絶えず干ばつに悩まされた。水田
による米の安定的な生産が出来ない土地であった。そのため米は贅沢品であり代用食として
麦などが生産されるようになったようだ。その代用食は現在「さぬきうどん」として全国的
に知られるようになった。「さぬきうどん」の創始者は郷土の偉人で「多才な天才」と称さ
れる弘法大師・空海と伝承されている。唐に留学した大師は、密教だけでなく先端の土木・
治水技術も習得し、帰国後、讃岐国に戻って水田の水を確保する満濃池(日本最大の灌漑用
のため池)の大改修工事に携わっている。同時に唐で盛んであった麺料理の製法も伝授した
と伝えられる。
◇このような天才の逸話は、イタリアにもある。「万能の天才」レオナルド・ダ・ヴィンチと
地中海式食事の代表的米料理リゾットとの関係である。ヨーロッパは気候風土から、米では
なく麦の生産が主である。500年前、北イタリアの領主は、ポー川流域にある未開発の低湿
地帯で米づくりを試みていた。米の大規模な生産のためには、灌漑施設が必須であった。
レオナルド・ダ・ヴィンチがこの灌漑施設の構築に貢献したという説である。彼の手稿には、
水路の設計、運河の建設、水力機械のスケッチなどが含まれており、彼がミラノの近郊を流
れるポー川の水路計画に携わったという記録が残っているからだ。現在、ポー川流域は、毎
年150万トンの米が生産されるヨーロッパ最大の米の産地となっている。ここではじまった
米づくりが現在のリゾットにつながるのである。
◇「令和の米騒動」の決着は、現時点では定かではない。米の高騰の原因として、減反政策、
生産コストの急激な高騰、生産調整の失敗、農家の高齢化と後継者不足など、政治・経済的
要因が指摘されている。日本の自然風土を考えれば、米が主食であることに変わりなく、米
の生産力が不足しているわけでもない。「令和の米騒動」は、天才の知恵を借りるまでもなく、
解決できる問題だろう。