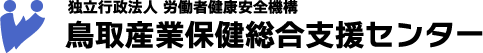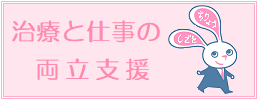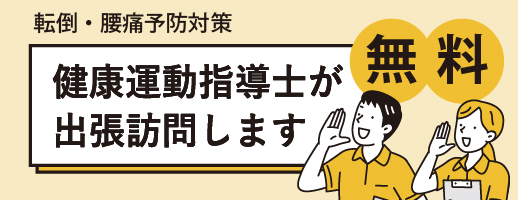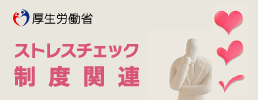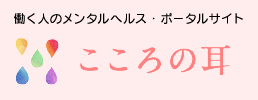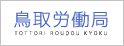鳥取産業保健総合支援センター 所長 黒沢 洋一
◇
『日本の家屋は寒い』
◇
我が国の月別死亡統計によると、死亡率は冬季(12月〜3月頃)に高くなり、1月頃にピークを迎える傾向が強く、夏場には減少します。
この冬季の死亡増加は世界的にも見られる現象で、「冬季超過死」と呼ばれています。一般的には、血圧の上昇や心疾患・脳血管疾患
の悪化、インフルエンザなどの感染症の流行、呼吸器疾患の悪化などが要因と考えられています。この冬季の過剰死亡を防ぐことは、
公衆衛生学における重要な課題の一つです。
◇しかし、冬季の死亡増加率に関しては、興味深い現象も観察されています。寒冷地である北海道と比較して、本州以南の温暖な地域
の方が冬季の死亡増加率が高い傾向があるのです。欧州でも同様に、寒冷な北欧よりも温暖な南欧の方が冬の死亡増加率が高いとされ
ています。その理由の一つとして、冬の室温の違いが指摘されています。寒冷地では、断熱材や暖房設備が整っており、室内は常に暖
かく保たれています。一方、温暖な地域では防寒設備が十分ではなく、冬の家屋は比較的寒い状態にあります。冬季の室温と健康との
関係についてはさまざまな研究が行われており、2018年に世界保健機関(WHO)は「寒さによる健康への悪影響から住民を守るため、
室温を十分に高く保つことが重要である」と提言しました。温暖・寒冷いずれの気候の国においても、冬季の室温は18℃以上に保つこ
とが推奨されています。
◇ある調査によれば、この条件を満たす日本の住宅はわずか1割にすぎないという結果でした。日本の家屋は寒いのです。同調査による
と、在宅中の居間の平均室温は北海道が19.8℃で、全国でもっとも暖かく、最も寒かったのは私の郷里である香川県で、13.1℃でした。
瀬戸内であっても冬の朝は零度近くまで冷え込みます。冬の朝、寝床から這い出すには気合が必要でした。当時は「冬だから部屋が寒
いのは当たり前」と思っていました。
◇近年、寒くなると呼吸器系疾患で体調を崩すことが増えてきました。昨年末は暖房器具の故障もあり、例年になく部屋が寒く、その
せいか咳がひどく、年末年始の外出も控えることになりました。これからは室温18℃以上を目指してみようと思います。
*伊香賀俊治 住宅の温熱環境と高齢者の健康 応用老年学 第17巻第1号 2023.8
鳥取産業保健総合支援センター 所長 黒沢 洋一
◇
『T細胞と衛生管理者』
◇10月、二人の日本人がノーベル賞を受賞するという快挙に、日本中が沸きました。ノーベル生理学・
医学賞の坂口志文大阪大学特任教授とノーベル化学賞の京都大学の北川進特別教授です。
◇坂口志文大阪大学特任教授は、病原体を攻撃する免疫細胞の中に、免疫反応の暴走を止めるブレーキ
役の「制御性T細胞」を発見し、受賞に至りました。免疫細胞が、誤って正常な細胞に攻撃することに
よりアレルギーやリウマチなどが生じますが、「制御性T細胞」の働きを強めれば、これらを抑えること
が期待されます。また、がん細胞は「制御性T細胞」を利用して、免疫系からの攻撃を回避しているため、
「制御性T細胞」の機能を弱める薬物は、新たな抗がん剤となる可能性があります。
◇京都大学の北川進特別教授の受賞理由は「多孔性金属錯体」の開発でした。「多孔性金属錯体」は、ジャ
ングルジムのような構造を持った金属と有機物の複合体で、その穴の中に、狙った気体の分子を吸着し貯
蔵することができる機能があります。CO2を優先的に吸着する「多孔性金属錯体」を用いれば、発電所や
工場から排出される排ガスからCO2を分離・回収することが可能となります。地球温暖化の防止にもつな
がることこそが受賞の決め手になったようです。
◇さて、「制御性T細胞」と聞いて、私が講師をつとめる衛生管理者講習会で使用している衛生管理テキス
ト(中央労働災害防止協会編)が頭に浮かびました。このテキストの労働生理の分野では、以下のような
記載があります。「リンパ球は、白血球の約30%を占め、リンパ節、胸腺、脾臓のリンパ組織で増殖し、
T細胞やB細胞などの種類があり、免疫反応に関与する。」「免疫に関する細胞には、主に、T細胞(リンパ
球)、B細胞(リンパ球)、マクロファージがある。T細胞(リンパ球)は、骨髄でつくられ、胸腺に移動し、
増殖・成熟する。・・・T細胞には、ヘルパーT細胞、細胞障害性T細胞などの種類があり、それぞれ違った
機能を持っている。細胞障害性T細胞は、細胞性免疫の中心となる細胞で、細菌やウイルスを攻撃する。
B細胞は、体液性免疫において中心的な役割を担い、ヘルパーT細胞によって活性化されると形質細胞に変
身し、抗体を放出するようになる。・・・」。さすがに「制御性T細胞」の記載はありませんが(いずれ
「制御性T細胞」も追記されるでしょう)、免疫に関する専門的な知識は、衛生管理者(第一種・第二種と
もに)に求められる幅広い知識の一部を構成しています。労働安全衛生の分野では、特に人の健康や職場
環境の管理に関する内容が多岐にわたり、その中には複雑で理解が難しい免疫の仕組みも含まれます。
私自身、T細胞やB細胞の働きについて説明する際、どのようにすれば受講者の興味を引き、理解を深めて
もらえるか不安を感じていました。しかし、今回「制御性T細胞」が注目を集めたことで、免疫の仕組みに
対する関心が高まっていると感じています。そのため、T細胞やB細胞の役割について詳しく説明しても、
衛生管理者を目指す受講者の方々に興味を持って耳を傾けてもらえるのではないかと期待しています。
*T細胞は、骨髄で産生された前駆細胞が胸腺で分化成熟します。T細胞の「T」は、胸腺(Thymus)に由来
しています。
*B細胞は骨髄で生成され、成熟します。B細胞の「B」は、骨髄(bone marrow)に由来しています。
鳥取産業保健総合支援センター 所長 黒沢 洋一
◇
『「令和の米騒動」と「天才」』
◇
◇米の値段が高騰し、「令和の米騒動」という状況になっている。日本の米の年間消費量は、
およそ700万トン、世界で9番目の消費量である。ただ、一人当たりの年間消費量は、1962
年をピークに一貫して減少傾向にある。1962年118.3キロだったのが、2022年には50.9キロ
まで減少した。米の高騰により、消費者の米離れが進むことが懸念される。
◇米離れといえば、私の故郷、香川県、讃岐国は、元々コメ離れした地域といえよう。讃岐
国は瀬戸内式気候で降雨量が少なく、大きな川もないため絶えず干ばつに悩まされた。水田
による米の安定的な生産が出来ない土地であった。そのため米は贅沢品であり代用食として
麦などが生産されるようになったようだ。その代用食は現在「さぬきうどん」として全国的
に知られるようになった。「さぬきうどん」の創始者は郷土の偉人で「多才な天才」と称さ
れる弘法大師・空海と伝承されている。唐に留学した大師は、密教だけでなく先端の土木・
治水技術も習得し、帰国後、讃岐国に戻って水田の水を確保する満濃池(日本最大の灌漑用
のため池)の大改修工事に携わっている。同時に唐で盛んであった麺料理の製法も伝授した
と伝えられる。
◇このような天才の逸話は、イタリアにもある。「万能の天才」レオナルド・ダ・ヴィンチと
地中海式食事の代表的米料理リゾットとの関係である。ヨーロッパは気候風土から、米では
なく麦の生産が主である。500年前、北イタリアの領主は、ポー川流域にある未開発の低湿
地帯で米づくりを試みていた。米の大規模な生産のためには、灌漑施設が必須であった。
レオナルド・ダ・ヴィンチがこの灌漑施設の構築に貢献したという説である。彼の手稿には、
水路の設計、運河の建設、水力機械のスケッチなどが含まれており、彼がミラノの近郊を流
れるポー川の水路計画に携わったという記録が残っているからだ。現在、ポー川流域は、毎
年150万トンの米が生産されるヨーロッパ最大の米の産地となっている。ここではじまった
米づくりが現在のリゾットにつながるのである。
◇「令和の米騒動」の決着は、現時点では定かではない。米の高騰の原因として、減反政策、
生産コストの急激な高騰、生産調整の失敗、農家の高齢化と後継者不足など、政治・経済的
要因が指摘されている。日本の自然風土を考えれば、米が主食であることに変わりなく、米
の生産力が不足しているわけでもない。「令和の米騒動」は、天才の知恵を借りるまでもなく、
解決できる問題だろう。
鳥取産業保健総合支援センター 所長 黒沢 洋一
◇
『職場における熱中症対策の義務化』
◇
◇全国的に熱中症に気をつけなければならない季節となった。職域でも熱中症による労働災害が
重要な課題の一つとなっている。熱中症による休業4日以上の死傷者数は年間千人を超えている。
◇従来は製鉄工、硝子工、ボイラーマンなど特殊な高温環境の労働で発生していたが、近年、建
築業など戸外労働での熱中症の発生が多くなっている。職場の熱中症対策として、暑さ指標(W
BGT)に対応した作業時間の短縮や休憩の確保、定期的な水分や塩分の補給、通風や冷房などに
よる環境整備、身体の不調に応じた適切な処置(身体冷却や医療機関への救急搬送)を行う必要
がある(令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱 厚生労働省)。
◇6月1日より、労働安全衛生規則が改正され、職場の熱中症対策が義務化された(労働安全衛生
規則の一部を改正する省令の施行等について (令和7年5月20日付け基発0520第6号))。過去3年
連続で死亡災害が30人を超え、減少傾向にないこと、さらに今後気候変動により死亡災害が急増
するのではないかという危機感が今回の改正の背景にある。現場において、死亡に至らせないた
めの適切な対策の実施が必須となり、今回の改正により「体制整備」、「手順作成」、「関係者への
周知」が義務化された。対策を怠った場合は、罰則(6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)
が科される場合もある。
◇過去3年間の死亡災害の要因分析によれば、初期症状の放置・対応の遅れが主な要因であるこ
とが判明している。熱中症のおそれのある労働者を早急に見つけるためには、作業者本人や周り
が異変を感じた場合の通報体制を確立することや職場巡視の徹底が必要とされる。単独作業作は
できるだけ避け、単独作業をせざるを得ない場合には、深部体温を検知して危険を知らせるウエ
ラブルデバイス等の活用も有効である。異常を発見した後の手順も定める必要がある。医療機関
へ搬送する必要があるかどうか判断するための基準を定め周知しなければならない。迷った場合
には躊躇なく緊急搬送するほうがよいとされる。一方、緊急搬送の必要のない軽症者への対応も
定めておく必要がある。また、救急搬送を待つ間、作業着を脱がせて水かけるなどの身体冷却処
置も周知しなければならない。体温が40℃をこえる重症の熱中症は、生命の危険が非常に高い状
態で、いかに早期に体温を下げるかが生命予後を決定するからです。
◇猛暑の夏が始まろうとしている。熱中症対策で死亡災害0を目指しましょう。
鳥取産業保健総合支援センター 所長 黒沢 洋一
『新型やくも』
◇
◇ゴールデンウイーク中の移動に車ではなく新型特急やくもを利用した。振り子電車の
特急やくもが苦手なのだが、昨年デビューした新型やくもの評判がよかったので利用す
ることになった。新型やくもに採用された最新技術の「車上型の制御付自然振り子方式」
により乗り心地が格段に向上したといわれる。以前の「自然振り子式」だと、カーブに
入って遠心力が働いてから揺れるため、揺れが遅れて生じ、急に大きく揺れる。また、
直線でも高速になると細かな揺れが生じやすいといわれる。最新の「車上型の制御付自
然振り子方式」では先頭車に搭載したジャイロセンサが走行位置を正確に把握し、曲線
の入口にあわせて車体を傾斜させるなど揺れを精密に制御しているという。
◇以前の特急やくもには車内販売があった。カニのお弁当、アルコール類やつまみなど
が売られて活況を呈していた。一方で、揺れの中、販売車を押しながらの販売員の移動
は見るからに大変そうだった。このような交通機関従事者の作業関連疾患として、全身
振動による障害が知られている。全身振動による障害では、短期的にはめまい、頭痛、
気分不快などの自律神経症状がみられるが、長期的には、腰痛などの筋骨格系障害、循
環器系、消化器系、泌尿器系の障害が問題となる。振り子電車の車内販売員の身体的負
担は産業保健分野の課題となっていたようで、特急やくもの車内販売員の健康調査が行
われていたと記憶している。そのやくも号の車内販売は2009年9月に廃止されたようだ。
乗客の減少等による売り上げの減少が主要因であろうが、販売員の負担も一要因であっ
たのだろう。
◇苦手とは言いながら、新幹線に接続する特急やくもはよく利用した。ただ、利用時は
体調を万全にしておく必要があった。車内では、水分以外の食べ物は摂取しないように
し、もちろん読書も控え、できるかぎり眠るようにしていた。特急やくも利用時のルー
ティーンである。このルーティーンをしないとたいてい気分が悪くなった。今回、行き
の新型やくもでは、大きな揺れをほとんど感じることはなかった。そこで、帰りの新型
やくも号では飲食を試してみた。おにぎり2個を食べたが、気分よく過ごせた。次は読書
を試してみようと思う。