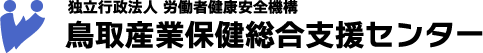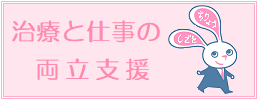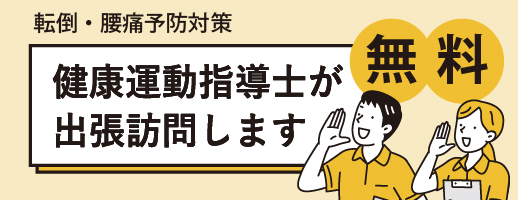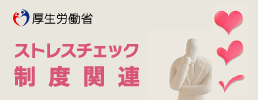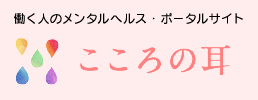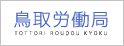鳥取産業保健総合支援センター 所長 黒沢 洋一
『温室効果ガス削減』
◇温室効果ガス世界資料センターによると2023年の大気中の二酸化炭素の世界平均濃度は、
前年と比べて2.3ppm(0.00023%)増えて420ppm(0.042%)となっている。産業革命以
前の値と推定される約280ppm(0.028%)と比べて、1.5倍に増加している。大気中の二酸
化炭素などの「温室効果ガス」は、地球の表面から逃げようとする赤外線(780~10万nm
の波長域の光で熱作用を有する)を吸収し、さらに赤外線を放出したりする。放出された
赤外線の一部は地表面に戻ってくるので、温室効果ガスには地表面付近をあたためる効果
があるとされる。プリンストン大学の真鍋淑郎博士は1960年代からこのような温室効果ガ
スの物理的作用と気象要因を考慮したシンプルなモデル(気候モデル)を作成して地球の
気温を計算した。試みに大気中の二酸化炭素濃度が当時の0.035%から2倍に増えるとどう
なるか計算したところ、地表付近の温度が2℃程度上がるという結果を得た。これが、地球
温暖化に関する研究の始まりと考えられている。真鍋淑郎博士は、2021年に気候モデルの
業績でノーベル物理学賞を受賞された。
◇公害などの環境問題に苦しんだ歴史のある日本は、京都議定書の策定に尽力するなど地球
温暖化対策に意欲的に取り組んできた。京都議定書とは、1997年12月に定められた気候変動
への国際的な条約である。先進国の排出する温室効果ガスの削減について、法的拘束力を持
つ数値目標が設定された。京都議定書の後継である「パリ協定」では先進国・途上国関係な
くすべての締約国が対象となって温室効果ガスの削減目標を示すことになっている。今年の
1月、温室効果ガスの排出量が世界第2位のアメリカで、「パリ協定」から離脱する大統領
令が出された。「パリ協定」がアメリカ経済に悪影響を与え、不公平な負担であることを理
由に挙げている。これに対応して国連事務総長は「アメリカ国内の都市や州、企業が他の国
々とともに、低炭素で強じんな経済成長に取り組み、引き続きビジョンとリーダーシップを
発揮することを確信している。」とコメントしている。
◇日本は新たな温室効果ガスの排出削減目標を「2035年度に2013年度比60%減、2040年度
に同73%減」に決め国連に報告した。ただ、産業革命からの気温上昇を1.5℃以内に抑える
「パリ協定」の水準(日本では2013年度比66%に相当するとされる)を下回ることになる
ので、日本の姿勢に批判があることは知っていたほうがよいだろう。
鳥取産業保健総合支援センター 所長 黒沢 洋一
『冬の転倒災害』
◇冬の山陰は、屋根の雪下ろしなどの除雪作業中の事故だけでなく、積雪や凍結に
起因する労働災害(転倒災害)も問題となる。厚生労働省・鳥取労働局によると、
毎年、鳥取・島根両県で数十件の積雪や凍結に起因する転倒災害が発生している。
そのため鳥取労働局は、「冬季のstop!転倒災害」を提唱している。その内容は、
事業所での転倒防止対策として凍結危険箇所の把握、凍結危険箇所の⾒える化、
通勤・帰宅への配慮、転倒防止マットの設置、危険箇所の凍結防止、4S(整理・
整頓・清掃・清潔)の徹底などである。転びにくい歩き方として、滑りにくい靴を
はく、小さな歩幅でゆっくり歩く、両手はポケットに入れないことなども紹介し
ている。
◇転倒は、移動中に発生することが多く、駐車場から職場への通路での転倒災害
が頻繁にみられる。転倒災害の防止の観点から、駐車場から職場につづく通路の
除雪や凍結防止は必須の対策であろう。また、高年齢労働者は、転びやすく骨折
しやすいので注意が必要である。積雪や凍結に起因する転倒災害の8割が50歳以
上の高年齢労働者である。厚生労働省のエイジフレンドリーガイドラインにある
ように、高年齢労働者の身体的状況に応じた適正配置、環境整備、転倒予防体操
などの対策が重要となる。
◇※参考:エイジフリーガイドライン
◇ (高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン)
◇◇◇◇ ◇https://www.mhlw.go.jp/content/001107783.pdf◇(R5.10)
鳥取産業保健総合支援センター 所長 黒沢 洋一
『雪下ろしと地方創生』
◇2025年は、仕事始めから今シーズン最強の寒波により、日本海側を中心に大雪となった。
屋根の雪下ろしなどの除雪作業中の事故が連日報道された。青森県は10日に大雪被害として、
死亡者7人を含む死傷者は102人に達したと報告した。これまでも豪雪地帯では、屋根の雪下
ろしなどの除雪作業中の事故が多く発生し、雪が多い年には、年間1000件以上の事故が発生
し、100人以上が亡くなるなど深刻な被害となっている。国土交通省は、除雪作業中の屋根か
らの転落事故のほか、転倒、除雪機による事故、落雪による事故、水路等への転落事故など
の防止のための注意事項を「雪下ろし安全10箇条」として取りまとめている。
第1条では、「安全な装置で行う」として、安全帯としてフルハーネスを使用し、命綱はアン
カー(ない場合には屋根の雪を下す反対側の柱、固定物)にしっかり固定とある。屋根の雪
下ろし作業は命がけの重労働である。
◇近年の傾向として、人口減少・高齢化により雪処理の担い手が不足し、高齢者を中心とし
た除雪作業中の事故が多く発生している。豪雪地帯の安全・安心な暮らしの確保を図る必要
があるとして、国土交通省は、地域における共助除排雪体制づくりを推進している。ただ、
限界集落といわれるように集落の共同活動の機能が低下しており、共助体制を維持するのは
容易ではない。やはり、人口減や社会的な基盤の維持など地方が抱える課題の解消をめざす
地方創生といった観点が必要なのだろう。政府の看板政策である地方創生に期待したい。
◇
◇
※参考(国土交通省 「雪下ろし安全10箇条」)
◇https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/chisei/kokudoseisaku_chisei_tk_000139.html
鳥取産業保健総合支援センター 所長 黒沢 洋一
『マイコプラズマ肺炎』
◇8年ぶりにマイコプラズマ肺炎が大流行しています。マイコプラズマ肺炎はマイコプラズマ・
ニューモニエという細菌が原因の病気です。感染経路は主に咳やくしゃみによる飛沫感染と接
触感染で、患者は1~14歳に多く、家族内や学校、会社などでしばしば集団発生が起こります。
潜伏期間は感染後2~3週間程度である。初期症状として発熱や倦怠感、頭痛などが現れ、発症
後3~5日で咳の症状が出るようになります。咳は、次第に強くなり解熱後も3~4週間続き
ます。一般に、軽症で済みますが、一部の人は脳炎など重症化することもあります。
◇マイコプラズマは分類上細菌に属する微生物ですが、一般の細菌より小さく、細菌とウイル
スの中間のような性質を持つのが特徴です。マイコプラズマには細菌のもつ細胞を保護する外
壁がありません。そのため、細菌にあるこの壁を壊して細菌を殺す作用を有するペニシリン、
セフェム系などの代表的な抗菌薬は、マイコプラズマに対して全く効果がありません。マイコ
プラズマ肺炎では、通常の肺炎では用いられないマクロライド系抗菌薬が第一選択となります。
◇マイコプラズマ肺炎では罹患後の免疫は長くは維持されないので、3年~4年ごとに流行を繰
り返すようです。4年ごとに開催されるオリンピック開催年に流行することが多いので、俗称で
「オリンピック病」とも呼ばれています。前回流行した8年前の2016年は、リオデジャネイロ・
オリンピック・パラリンピックの年でした。その後新型コロナウイルス感染症が流行し、マスク
着用、手洗いの励行等、基本的な感染症対策が行われたためマイコプラズマ肺炎は流行しません
でした。昨年、新型コロナウイルス感染症が、5類感染症への移行に伴い、基本的な感染症対策
が緩和されたため、今年8年ぶりの大流行となったようです。今年は、パリ・オリンピック・パ
ラリンピックの年でもありました。ただ、マイコプラズマ肺炎流行とオリンピック・パラリンピ
ックが直接関係しているわけではなく、たまたま周期が一致しているだけと考えられています。
◇マイコプラズマ肺炎は、風邪に似た症状と咳のみの軽症で済むことが多いため、正確な診断が
なされないままに治癒している例も多いようです。私も、以前頑固な咳が続き、咳以外の症状が
ないので放置したが、2~3か月してようやく咳は収まった経験があります。ただ、睡眠や仕事
に若干の影響が出たと記憶しています。いつ頃であったか振り返ると、8年前の2016年でした。
今から考えると、マイコプラズマ肺炎だったかもしれません。受診していたら、もっと早く咳は
止まったのにと後悔しました。次回オリンピック・パラリンピックは、ロサンゼルスで2028年
開催予定です。2028年は、マイコプラズマ肺炎に要注意かもしれない。
鳥取産業保健総合支援センター 所長 黒沢 洋一
『世論調査はあてにならない』
アメリカの大統領選挙はまれにみる接戦であると各種世論調査が伝えられ、決着には
数日かかるとの見方が大半であった。だが、決着はすぐについた。そのため、世論調
査はあてにならないといわれる。
◇対象集団(母集団)を少数の標本(サンプル)から予測する世論調査は、統計学の理
論に基づく理想的な方法を用いればかなりの精度(推測が間違う確率5%未満のよう
に)で推測できる。理想的な方法の最も重要な点は母集団を代表するようなサンプル
が選ばればれることである。方法の誤りによる失敗例が1936年のアメリカ大統領選挙
における世論調査である。保健統計のテキストなどにも紹介される有名な事例である。
1936年のアメリカ大統領選挙は再選を目指す民主党のフランクリン・ルーズベルト候
補と挑戦する共和党のアルフレッド・ランドン候補によって争われた。大手雑誌のリ
テラリー・ダイジェストが自誌の購読者、電話利用者等の名簿等から無作為に調査対
象者を選び共和党のランドンと予測した。結果はフランクリン・ルーズベルトの大勝
であった。当時電話の普及が進みつつある段階で、電話を所有していた人には比較的
裕福であるという傾向があった。当時、共和党は比較的裕福な層が支持基盤で、民主
党は比較的貧しい層が支持基盤であった。そのため、電話帳から選んだ調査対象には
初めから共和党優位の偏りがあり、誤った予測結果となった。その後は電話の普及が
進んだので、このような偏りはほとんどないと考えられている。このため、新聞社な
どが行う調査方法は、コンピューターが無作為に決めた電話番号に調査員が電話して
回答を集める方法が一般的である。最近では、回答率の低下やコスト上昇の関係で、
インターネット調査への移行も進んでいるようだ。
◇対象者の選び方のほかに、回答する側の問題もある。例えば個人の収入に関する質
問は、無回答が多くなるなど、正確な情報が得にくいことが容易に推測される。基本
的な情報である年齢でさえも、正確な情報は得にくいことが知られている。実年齢よ
りも若く申告する傾向があるのだ。最近の大統領選挙では、意中の候補の名を表明し
ない、うその申告をするなど、いわゆる隠れ支持者の存在が調査結果をかく乱する要
因となっている。ある世論調査会社は「隠れ支持者」の存在を独自に調査・評価して
補正する方法を用いて今回の大統領選挙結果を正確に的中させている。多数の世論調
査が出てくるが、このような調査能力に優れた世論調査会社の結果を信頼すればよい
のではないかと思う。ただ、この会社も前々回2016年の大統領選は的中させているが、
前回2020年は外しているようだ。「隠れ支持者」の存在を過大に評価しすぎたせいかも
しれない。世論調査結果は、あくまでも参考資料の一つとしてみるのがよいだろう。