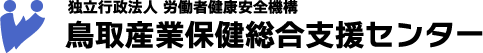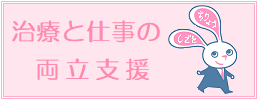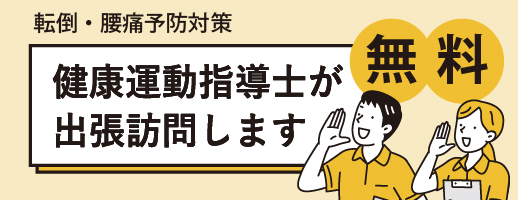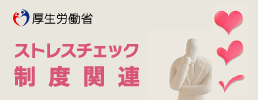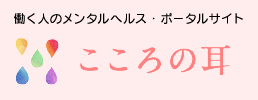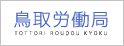鳥取産業保健総合支援センター 所長 能勢 隆之
いよいよ平成29年度(2017年度)が始まりました。4月は、新入社員や転勤により職場を異動し、仕事に慣れていない労働者が作業現場で活動を開始する時期です。
この時期は、はじめて社会に参加し会社で働く者や、単身赴任となったり、生活管理に困難を感じる者、また仕事内容に興味が持てなかったり、新しい人間関係が上手につくれないなど健康に破たんを起こす場面に遭遇しやすい機会でもあります。とくにメンタル不調をきたし、それをきっかけに精神的障害を発生する人もいますので、十分にこれらの変化に配慮し、体調不良をおこすことのないように職場全体で気を配ることが必要です。
まず何はともあれ、どのような作業環境、作業内容に就くにあたっても、健康である事が重要な事は言うまでもありません。新に着任した作業環境(大気、騒音、有機溶剤などの化学物質、石綿などの粉じん、高温、高圧作業、電離放射線取扱い作業など)に適切に慣れることや、労働時間の変化、夜勤業務や、人間関係に身体の調子を崩さないように自身で努力したり、職場の他の労働者や管理者等が見守り、支援することも大事です。
このため労働安全衛生法が昭和47年に制定され、その目的を達成するため事業主や事業場に自主的に労働安全衛生活動に取り組むことを義務づけています。
この対策のひとつに「健康診断」があり、医学的検査を行い、医師の診察などを合わせて主に労働者の身体的変化と健康度のチェックを行っています。まず、採用時に「雇い入れ健診」、継続して働く者の「定期健診」があり、その基本的な検査項目に、検尿、血圧、血液一般、血糖値、肝機能、心電図、胸部レントレゲン検査等が実施され、過重労働の健康への影響のチェックや、がん、心臓病などの生活習慣病等の予防につなげています。
その他に特殊な作業(有機溶剤作業、粉じん作業、高気圧作業、電離放射線や石綿取扱い作業など)に従事する者について「特殊健康診断」を行い、身体影響のチェックと作業改善に繋げています。
今日では、職場のメンタルヘルス不調についての対策が重要となり、平成27年よりストレスチェック制度が創設され、労働者自身には、「ストレスの気づき」を促し、事業者には、集団分析によりストレスの原因となる職場環境の改善につとめることが努力義務とされ、職場のストレス低減に向けての実施を求められるようになりました。
労働衛生活動は労働者の健康の保持・増進を目指していますが対策の内容は、時代の変遷に合わせて、変化、改善されています。身体の健康のみに重点をおかれていた時代から、今日では、特に若い労働者については考え方も変わったことや、価値観が多様化し、生活が乱れることも多いことや長時間労働が強要され、健康にも影響を及ぼしていますので、生活管理や精神保健(メンタルヘルス対策)に重点が移りつつあります。
人間関係の希薄化、ニート現象、非常勤(非正規)・時間給労働者等の増加も、作業環境を適切にするための新しい課題です。
また、労働者の高齢化と労働者不足は解決困難ではありますが、改善すべ喫緊の課題ともなっています。労働者は企業のみならず、日本の経済社会を健全に発展させる原動力となりますので、労働安全衛生法の目指す「健康管理の実践は事業主や労働者自身の責務である」ことをとあらためて実践し、形あるものにすることが求められているのだと思います。
鳥取産業保健総合支援センター 所長 能勢 隆之
病気の予防や予後(転帰)について、今まで多数のことが研究されたり、臨床の現場で患者への説明につかわれています。また、病気の発生に関連する要因(広い意味での原因)も解明され活用されています。
感染症のように病原微生物の関与がなければ発症しない疾病などについては原因物質が比較的分かりやすいのですが、(しかし結核菌に感染しても結核症を発症しない人も多くあることも考慮に入れておくことも必要です)、病因が多数関与する場合(多くの病気はこの方が多い)には、病気の予防は単純ではありません。
発病についても、集団を対象として解明される確率(発病割合)で推測し、考えて説明するしかありませんが、個人一人一人にとっては発病した場合、集団確率で発生したのではなく、発生確率は100%です。
産業保健事業においては、病気の治療と職業生活を両立させて支援することにより、労働力不足が起きないように対策が急がれます。
しかし、これについては就労可能どうかを判断する医学的知見が明らかにされていなくてはならないのですが、一般的に多くの病気を個人的レベルにあてはめてみると次のような事が分っていません。
①治療を行うことにより、病気が就労可能な状態まで改善されているかどうか。
②病気の進行が、労働者の社会生活や就労を困難にする程度になるまで、どのくらいの期間がかかるのか。
③障害を残さないで就労可能な状態になるまで治癒するのか。
これらの事がある程度究明されていないと、休業措置や就労復帰の予測や判断の際に、一律にはいかない状況にあります。
病気の予防は、発病に関与する要因が多数あっても、主な要因がある程度分かっていればばく露させない事が可能です。
しかし、例えば、「たばこの喫煙」と「肺がん」の発生の関連は明らかになっていますが、「喫煙していない人」も肺がんを罹患するので、人体に影響を及ぼす要因と人体影響を明らかにすることは難しいのです。
また、「メンタルヘルス関係」の就労支援、特に「職場復帰」については、専門医を受診し主治医が職場復帰可能と診断されても、産業医も復帰可能とは判断しにくい場合があります。例えば一例として発達障害があり職場不適応となる若い労働者の場合でも、環境要因(出産時の親の年令、合併症などの要因も含む)や、遺伝要因などが絡んで発症しますし、類似の診断名が多く、専門医であっても診断名が一致しない場合や病気の状態が就労中や休業中などの環境要因の変化によっても症候が変動する為、同一の医師であっても診断について病気の経過中に異なる事例があります。
産業医は、職場復帰や就労支援を行う場合、職場の状況や個人的要素などを考慮して、たとえ治療中であっても職場に適応できるか、或いは職場が配慮できるかなどを考え、場合によっては事業主と職場環境の改善の可能性について相談しつつ判断をすることになります。
これらについて職場の同僚や関係者に理解できるよう説明し、了解を得る体制を整える努力をしないと、治療と就労の両立支援やメンタルヘルス不調者の職場復帰を可能にすることは出来ないと思います。
今まで医学では携わってこなかった難しい分野でありますので、不十分ながらも実践しつつ改善し、研究・研鑚をつむことにより目標が達成可能となることを願っています。
鳥取産業保健総合支援センター 所長 能勢 隆之
少子高齢化が進行するとともに、人口の年齢構成が変化する中、10歳ごとの年代別人口構成のピークは高齢の方向にシフトしています。
これに合わせ、労働人口もピークが高齢にシフトしているので、労働力を確保するために定年延長が検討され、或いは、産業分野によっては、実際に実施されています。このことは、高齢者が労働を継続できる健康と体力を維持し、定年後も労働可能な健康を維持しているという裏付けでもあります。
それを受け、若者も高齢者も、男性も女性も、障害のある者も、国民の一人ひとりが自分の希望する職場や業務に配置され、それぞれの能力を発揮して働くことが出来る労働現場を確保することが国策としてとられつつあります。
そのためには、適正な労働条件や安全で衛生的な仕事を数多く確保し、現在の労働のあり方を改革に向け、雇用改善が必要となっています。
このような観点から、同一労働同一賃金の実現に向けて取組み、非正規雇用の拡大を止めるとともに、非正規労働者の待遇改善、長時間労働の是正、また、女性・若者、高齢者、障害者、病気治療中の者など、多様な人材の活躍を促進することが施策にとられる様になりました。
これらの施策のなかで、特に女性の労働力の確保は必須であり、「女性活躍推進法」が実際に施策となるような動きが提案されています。また、「一億総活躍社会」を支えるため、平成29年1月に施行された、「改正育児・介護休業法」及び、「改正男女雇用機会均等法」により、妊娠・出産・育児休業・介護休業等の制度を周知して、上司・同僚等による就業環境を害する行為(ハラスメント)を防止するため、雇用管理上必要な措置を事業主に義務づけられました。今後これらの改正を周知し、理解を深め実施されることを目標に産業保健総合支援センターの研修内容にも多数計画されるようになります。
これを進めるためには、多数の解決するべく労働体制や職場環境の改善が必要ですが、まず男性女性も、事業主も労働者も今までの価値観と考え方を改める事が必要です。
一例として、医学医療の分野においても、女性の医学生の人数がクラスの半分を占めるようになり、将来、女医が増加することが予測されます。男性医師を中心に医療体制や患者ケア体制がとられていたので、24時間患者のケアをすることを、当たり前としてきた主治医体制を考え直す必要があります。
女医も結婚し、育児に携わるのは当たり前である今、主治医の概念で患者ケアに携わる事は困難となる事が予想されます。看護体制のように、医師も3交替制で患者の治療にあたれるような、思い切った考え方を取り入れなければ、医師の労働力の確保と医療機関の経営が困難になります。
しかし、患者側においても自分の気に入った医師に治療を続けて貰いたいと思っているし、医師が時間がきたら交替して治療にあたる事を受け入れられるであろうか疑問です。
特に、医療を経営する側、医療行政を立案・実施する行政側の考え方を早急に改革しなければ、医療現場はスムーズに医療の目指すあり方を維持出来なくなるのです。これは、医療現場の問題でなく、それぞれの業態で、それぞれ固有の課題があると思われますので、種々多様な機能・能力のある労働者を職場に確保していくためには、規則や法律を新設、改善するのも必要でありますが、それ以上に従来正しいと思われていた考えや体制を見直し、あらゆる人を受け入れることが必要であると強く考えるようになりました。
鳥取産業保健総合支援センター 所長 能勢 隆之
新年明けましておめでとうございます。
年頭にあたり、今年の社会情勢をみながら産業保健の進む道を予想してみたいと思います。
「産業保健」は職域で働く人を対象とした健康問題の対策をする事と健康管理の知識を普及し、必要で適切な技法を実践し、「労働者の健康に貢献すること」にあります。そして、この分野に関連する対象人口は国民の8割にもなり、公衆衛生活動の最も大きな対象集団であります。労働者の健康管理は近年の就業構造の多様化により急速に変遷しています。明治時代の感染症対策、特に結核対策に始まり、職業現場でおこる特異的な有害ばく露要因による健康影響の調査、臨床診断、治療、そして予防対策を講じてきました。そして、これらに関する研究開発により職業性疾病等を減少させてきました。
最近では、人口の少子高齢化にともない、労働者も中高年齢者が増加し、循環器疾患やがんに罹患する或いは罹患しながら就労を可能にする職場の体制づくりが課題となっています。
そして、労働形態の多様化によって顕著となってきたストレス対策としての「メンタルヘルス予防事業」、更に日本の文化としては、「よく働く事を美徳」としてきましたが、働き過ぎる事が良くない(パラダイムシフト〔従来の常識を全く新しいものに替えること〕)と考えるようになった事と、いわゆる事務的で規定通りに行う作業はコンピューターに任せたり、価値を生みにくい作業はAI(人工知能)に代替しようという新しい「産業革命」が進行しています。
これに合わせ過労死裁判以降は、事業主も、労働者が疲労や心理的負荷が過度に蓄積して心身の健康を害することが無いように注意しなければならない事を認識するようになりました。
この働き過ぎを当たり前とする考え方は政治主導で起こったグローバル資本主義に負けまいとする政策と新自由主義思想の普及によるものでありますが、この働き過ぎ等による健康障害の発生は、本質的な資本主義の欠陥と問題点が表面化してきたためでもあります。
経済分野においては、自由競争の中で上手に稼ぐことが資本主義の正義であると考えるため、自由競争で敗れたら職を失うことになり、その事は自己責任であるとし、かつ格差拡大の政策を正当化するようになりました。
企業もこの自由競争の中におかれ、事業主も負けまいと努力することとなり、その結果、企業経営のための「積極的経費節減」と「非正規労働者」の雇用拡大、そして労働時間を守られない等の「労働強化」を推し進めざるを得なくなっているのです。
こうした事が「ブラック企業」を出現させる一因となっています。
日本社会での資本主義、自由競争は、心豊かに暮らせる社会を作ろうという国民的合意のもとに発展し、格差の少ない中流的資本主義が実践され運営されてきました。
しかし、年末から年始にかけて米国大統領候補のトランプ氏による政策的発言に世界が影響を受け、いわゆる政界・財界にトランプ現象が起こっています。新しい米国中心の世界経済情勢により、日本国内の価値判断基準が変化し、労働環境に影響を与えることが予想されます。
こうした動きの中で、日本的価値判断基準をもとに考えられ、労働者の福祉の向上に貢献する事を目指してきた日本の「産業保健」をどのように構築していくのか、今日では先行き不透明な面もありますが、適切に対応していくことが必要であり、まさに正念場となる年と考えています。
鳥取産業保健総合支援センター 所長 能勢 隆之
今日まで労働の過重負荷がもたらす生態影響は、重たい荷物を持ち上げ人力で運搬したり、過酷で劣悪な労働条件下の職場で働く労働者について発生する「健康障害」と考えてきました。
これらの作業は重機の導入、ロボット化、作業環境の改善や予防・対策などによって今日では目覚ましく改善されてきました。それに代わり、コンピュータ化による労働密度の高まり、残業・休日出勤の時間外労働の常態化による長時間労働など過重で過密な労働負担が加わりテクノストレス等も重なって健康破壊が発生するようになりました。
肉体疲労と精神疲労が蓄積し、これらが重なって過労状態が続き、かつ慢性化し、これによって病的疲労(機能的変化の状態から異質的障害をおこし不可逆的な変化が進んだ状態)が起こり、その中でも死に至る最も重篤な場合が「過労死」です。
これは、長時間労働、深夜勤労働、精神的負担の大きい労働環境(配置転換、出向、単身赴任等)、いわゆる過重労働などに起因する作業に従事し、疲労が蓄積し、過労状態が続く事により、生活習慣病のうち、循環器系の疾患(脳出血、クモ膜下出血、脳血栓、虚血性心疾患、急性心不全など)などが起こり、死亡した場合、業務上に起因したものとして労災認定とするのが適当であると考えるようになりました。
一方、過労死に関連する疾病は、労働に関連して発生するのみでなく、個人の素因や不摂生な日常生活(食生活、運動不足、家庭内ストレス、飲酒、喫煙など)によっても発病するため、職業関連疾病として判断する事が困難な事が多く、今までは労災認定がされにくかったのです。今日では、自殺も長時間労働に起因したものとして考えられる場合が発生しています。
そこで、判定をより容易にするため、定期的に職場での健康診断を受診し、日頃の健康状態を把握しておくことによって、日常の就労環境と関連するかどうかを判定し易くなるようにしておく必要があります。もし血圧などの異常所見が見つかれば、産業保健スタッフなどに相談し、保健指導を受けて改善に努めます。かつ定期的に「メンタルヘルスチェック」などで職場のストレス状態を把握しておき、その上で不幸にも健康障害や死に至った場合に、職業に起因する「過労死」であると判断することが比較的容易になります。
医学的に判定するための過重負荷の決まった定義が特にあるわけではなく、異常な出来事に遭遇したり、予め決められている就業規則を大きく逸脱しての勤務状態であったり、特に過重な業務(企業や職種によっても異なる)に一定の期間従事した就業場所で発症した場合に、検討・審議されるので日常の仕事内容、勤務時間、健康状態を把握しておくことが必要です。
「過労死」の概念を取り入れたのは、労災補償認定の容易化を目的とするもののみではなく、循環器疾患も職業病の範ちゅうであり、長時間労働やストレスの多い作業環境での労働を異常なまでに強いる事のないように適切な改善を図り、健全な労働環境のもとで労働者が活動しやすくなり、更に企業の発展につながることを目指したものである事を改めて認識することにあります。