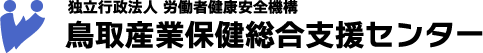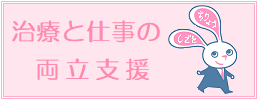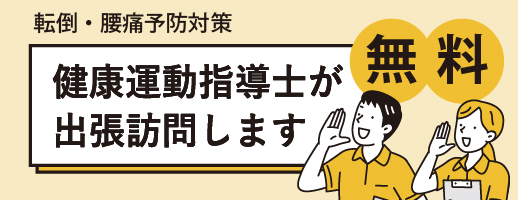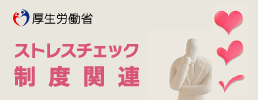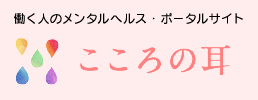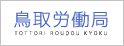鳥取産業保健総合支援センター 所長 能勢 隆之
産業保健の底流に労働者の健康保持増進そして疾病予防と生活支援の考え方が流れています。人は働きながら社会参加をすることによって、生きがいを持ち、収入を得て安定的社会生活を過ごすことができます。
国の施策としての「治療と職業生活の両立支援対策事業」は、産業保健の流れに沿って「病気になっても医療機関の外来で治療を受けながら働き続けたい」という人を支援することを目指しています。
この対策の背景には多くの要因がありますが、「平成22年国民生活基礎調査」の結果から、推計30万人以上の労働者が「がん」で通院しながら就労していることが明らかになり、また、平成28年の労働衛生統計においても(50人以上の労働者を雇用している事業場からの報告によると)、一般健康診断の結果で、労働者の半数を超える人に、健診項目の基準値の範ちゅうを外れた異常所見があるとされ、また、全く異常所見のない、いわゆる「健常者」が少なくなっているという調査結果が一つの理由になっています。
その上、労働者の年齢構成も高齢化が進み、かつ常勤労働人口そのものも減少していることもあり、将来の労働力不足対策の一環としても必要な事と考えられます。
以前から健全な国民や労働者を保持するため健康増進事業が実施されています。特に労働者を対象に、トータル・ヘルスプロモーション・プラン(THP)事業の提唱により、運動やパワートレーニングを取り入れた体力づくり運動が展開され、企業のみならず、これに興味を示した自治体も、市町村に健康増進センターを設置し、トレーニング用の健康器具を導入して、住民(労働者も含まれている)の体力向上に力を入れてきました。
しかし、自治体においては財政困難な状況になったり、参加者が思った以上に伸びなかった事などにより、この事業が削減されました。また各企業においては労働者の健康づくりに、トレーニング器具が必要となったので、健康増進車等を導入してサービスを行いましたが、種々の理由(時間がない、経費がかかるなど)により、企業が年に何回か開催するイベントで活用されるぐらいとなり、THP事業もうまくはいっていません。
最近、企業においても健康な労働者がいなければ企業の発展は見込めないと言われ、「健康経営」の考え方が取りあげられています。この考えも大変重要なことであり進化させていかなくてはならないと考えています。たとえ企業の経営が下降気味になっても健康経営の考え方が変わらないように維持されることを願っています。
さて、健康が多少害されても、労働力としては十分に活用出来る労働者が多くなったことや、労働力不足の対策にも就労支援が必要であることを述べましたが、企業を経営する人には対応が難しいこともあり、受け入れにくいこともありますので、健康づくり運動のように衰退してしまわないか気になるところです。
これからは健康にかかわる対策を行い、経営的効果をある程度明確に示すことが必要と考えます。もともと企業努力と理解により就労支援の考え方が企業に定着すると思うので、出来るだけ科学的に目に見えるように効果を示すことが必要です。
経営的効果をはかる推測方法として、費用効果分析という方法があります。この解析方法は産業保健分野では、あまり活用されていないと思われます。
それは、効果を分析する場合に、もともと負の費用効果が含まれているうえに、利益が出たかどうかが労働者や企業のメンタル的価値や健康経営など、心の豊かさにかかわる考えを入れなくてはならないからです。
病気の治療をしながらの就労については、労働者の生きがい、家族の安心をも含んだ企業の健全な考えが取り入れられねば、経営的に効果がある分析結果を出すことができません。
産業保健の取組は、必ずしも営利を目的とする企業には取り入れにくいものですが、福祉の向上を目指す企業活動がさらに社会の発展につながると理解され、就労支援をすることが必要であると企業経営のなかで定着することを願っています。
鳥取産業保健総合支援センター 所長 能勢 隆之
職場の健康管理は、いわゆる職業病(生産活動に従事することによって発生する健康障害で、腰痛症、騒音性難聴、振動障害、鉛中毒、じん肺症等をいう。)に限定せず、私傷病とされていた生活習慣病(一般に生活習慣が原因で発症する健康障害で、高血圧、脳卒中、心臓病、がん等をいう。)も作業関連疾患の範ちゅうに入れて対応することにより、これらの疾病の予防を含め、積極的に健康増進を推進するようになりました。さらに、職場の種々のストレスや人間関係に起因する心の健康の障害予防や改善に努めることが、メンタルヘルス対策として今日的主要プログラムになり、新たにがん患者などが治療をしながら就労が可能な環境をつくるなどの就労支援事業が実践されています。
このため、雇用時の健康診断や毎年の定期健康診断では健康診断で実施される医学的検査の結果が正常かどうかに注目されがちでしたが、それよりも労働者の健康状態を把握することによって、労働時間の短縮、作業転換、配置換えなどの健康診断の事後措置に役立てることが必要なので、①既往歴および業務歴の調査、②自覚症状および他覚症状の有無の調査が一層重要なものになっていることに気づかされています。
①既往歴および業務歴の調査は、今日では一事業場での永久就業は少なくなり、今現在の企業に採用されるまでに数種の職業に就労してきた労働者も珍しくなくなりつつある現状では、直近に実施した健康診断の結果を活用し健康状態を判断をするだけでは、健診事後措置に役立てるのには、不十分となりました。労働者を適正に配置するためには、以前の就業歴、既往疾患、服薬歴、喫煙・飲酒歴を把握し、かつ、現在罹患している疾病の状況も把握する必要があります。それによって就業以前の健康状態を調査し必要に応じて人事配置を考慮する事により、生活習慣病などの憎悪を予防するように努める必要がでてきました。
②自覚症状および他覚症状については、検査の基本は視診、聴打診、触診などの臨床診療手法による他覚所見検査を行い、そして既往歴、業務歴、生活状況、家族歴などと、就業するあるいは、就業している作業場の巡視の状況などと照合してさらに必要な検査項目を追加して選び、総合的に判断をしています。
特殊健康診断においては、取扱う化学物質や従事している作業環境などの健康影響の情報を把握し、労働者本人に中毒や障害の内容を説明するとともに関連する他覚所見を診察、記録しておいて、その後の障害等の判定や健康管理に活用するように努めています。
この①②の検査を行うとともに、その他の健康診断項目すなわち身長・体重・腹囲・胸部エックス線検査、血圧測定、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図を医師の判断により実施しますが、医学的に異常値のみのチェックを目的に行うのではなく、毎年同じ検査をくり返し行い変化の把握と作業環境の改善などの事後措置に役立て健康管理を行うことが、時代の変化に合わせた健康診断の現実的活用と考えています。このような理由から労働者の皆様には健康診断をぜひ毎年受けていただきますようにお願いいたします。
鳥取産業保健総合支援センター 所長 能勢 隆之
近年、産業保健の主要な課題が変化するなか、重要な役割を担う「産業医のあり方」が検討されています。
労働安全衛生法では、従業員が50人以上の事業場には、総括安全衛生管理者(業種・労働者数により設置が必要)、安全
管理者(同)、衛生管理者及び産業医などを選任することが定められています。
その中で、産業医として活動する者は、医師免許を有する者が医学に関する専門的知識に基づき、有害物を取扱う業務や夜間など
特殊な環境で作業に従事する労働者の健康管理、そして、いわゆる生活習慣病の予防のため労働者の相談にのったり、
就労環境の改善について必要な措置を事業主に指導します。
また、毎月1回以上の職場巡視(労働安全衛生規則の改正により、平成29年6月1日以降は、事業主から毎月1回以上産業医に
所定の情報が提供されている場合であって、事業者の同意がある場合には職場巡視の頻度を2ヶ月に1回とすることができるよう
になりました。)をしたり、最近では過重労働による健康障害の防止、メンタルヘルス対策、労働者の病気の治療と職業生活の両
立支援を行うなど、担う業務が増大しています。
さらに、衛生委員会に「産業医」として参加し、労働者の健康管理について専門的立場で説明したり、課題の提案などを行います。
そこで、産業医を法人の医師である代表者や病院の院長などが兼任している場合は、職務が適切に遂行しにくいことや労働者
の健康管理と人事などを含む事業経営上の利益が一致しない場合も想定されることから、これを禁止するため労働安全衛生規則
が改正され、平成29年4月1日から施行されることになりました。
労働安全衛生法が施行されるまでは、産業医の事業場での立場が明確でなく、かつ、事業主が産業医の依頼主となるため、適切
に勧告を行いにくい場合もありました。
しかし、労働安全衛生法に、産業医の立場は事業主と労働者の中間に位置し、中立的立場で衛生委員会で発言できるし、事業主
に勧告できるようになりました。また、労働安全衛生規則第14条第4項において、事業主は、産業医が勧告した内容を理由にして
産業医に対して、解任その他の不利益な取り扱いをしないようにしなければならないと産業医の立場が保護されたため、依頼主で
ある事業主に対しても、忖度なしに勧告できるなど産業医の職務が行い易くなりました。
よって、産業医は中立的立場で、労働者の健康管理にあたり、就労のあり方についても適切な判断をいたします。労働者は健全
で良好な作業環境で働くことは当たり前のことですので、もしも、職場や自身の身体に不都合が生じた場合には、産業医に相談して
下さい。
労働者不足の改善や健全な労働者を確保するため、メンタルヘルス不調の予防や病気の治療をしながら就労を継続することを
容易にするための事業場における「就労両立支援」などの種々の施策が始まりましたので、必要に応じて産業医を活用されること
を期待いたします。
鳥取産業保健総合支援センター 所長 能勢 隆之
いよいよ平成29年度(2017年度)が始まりました。4月は、新入社員や転勤により職場を異動し、仕事に慣れていない労働者が作業現場で活動を開始する時期です。
この時期は、はじめて社会に参加し会社で働く者や、単身赴任となったり、生活管理に困難を感じる者、また仕事内容に興味が持てなかったり、新しい人間関係が上手につくれないなど健康に破たんを起こす場面に遭遇しやすい機会でもあります。とくにメンタル不調をきたし、それをきっかけに精神的障害を発生する人もいますので、十分にこれらの変化に配慮し、体調不良をおこすことのないように職場全体で気を配ることが必要です。
まず何はともあれ、どのような作業環境、作業内容に就くにあたっても、健康である事が重要な事は言うまでもありません。新に着任した作業環境(大気、騒音、有機溶剤などの化学物質、石綿などの粉じん、高温、高圧作業、電離放射線取扱い作業など)に適切に慣れることや、労働時間の変化、夜勤業務や、人間関係に身体の調子を崩さないように自身で努力したり、職場の他の労働者や管理者等が見守り、支援することも大事です。
このため労働安全衛生法が昭和47年に制定され、その目的を達成するため事業主や事業場に自主的に労働安全衛生活動に取り組むことを義務づけています。
この対策のひとつに「健康診断」があり、医学的検査を行い、医師の診察などを合わせて主に労働者の身体的変化と健康度のチェックを行っています。まず、採用時に「雇い入れ健診」、継続して働く者の「定期健診」があり、その基本的な検査項目に、検尿、血圧、血液一般、血糖値、肝機能、心電図、胸部レントレゲン検査等が実施され、過重労働の健康への影響のチェックや、がん、心臓病などの生活習慣病等の予防につなげています。
その他に特殊な作業(有機溶剤作業、粉じん作業、高気圧作業、電離放射線や石綿取扱い作業など)に従事する者について「特殊健康診断」を行い、身体影響のチェックと作業改善に繋げています。
今日では、職場のメンタルヘルス不調についての対策が重要となり、平成27年よりストレスチェック制度が創設され、労働者自身には、「ストレスの気づき」を促し、事業者には、集団分析によりストレスの原因となる職場環境の改善につとめることが努力義務とされ、職場のストレス低減に向けての実施を求められるようになりました。
労働衛生活動は労働者の健康の保持・増進を目指していますが対策の内容は、時代の変遷に合わせて、変化、改善されています。身体の健康のみに重点をおかれていた時代から、今日では、特に若い労働者については考え方も変わったことや、価値観が多様化し、生活が乱れることも多いことや長時間労働が強要され、健康にも影響を及ぼしていますので、生活管理や精神保健(メンタルヘルス対策)に重点が移りつつあります。
人間関係の希薄化、ニート現象、非常勤(非正規)・時間給労働者等の増加も、作業環境を適切にするための新しい課題です。
また、労働者の高齢化と労働者不足は解決困難ではありますが、改善すべ喫緊の課題ともなっています。労働者は企業のみならず、日本の経済社会を健全に発展させる原動力となりますので、労働安全衛生法の目指す「健康管理の実践は事業主や労働者自身の責務である」ことをとあらためて実践し、形あるものにすることが求められているのだと思います。
鳥取産業保健総合支援センター 所長 能勢 隆之
病気の予防や予後(転帰)について、今まで多数のことが研究されたり、臨床の現場で患者への説明につかわれています。また、病気の発生に関連する要因(広い意味での原因)も解明され活用されています。
感染症のように病原微生物の関与がなければ発症しない疾病などについては原因物質が比較的分かりやすいのですが、(しかし結核菌に感染しても結核症を発症しない人も多くあることも考慮に入れておくことも必要です)、病因が多数関与する場合(多くの病気はこの方が多い)には、病気の予防は単純ではありません。
発病についても、集団を対象として解明される確率(発病割合)で推測し、考えて説明するしかありませんが、個人一人一人にとっては発病した場合、集団確率で発生したのではなく、発生確率は100%です。
産業保健事業においては、病気の治療と職業生活を両立させて支援することにより、労働力不足が起きないように対策が急がれます。
しかし、これについては就労可能どうかを判断する医学的知見が明らかにされていなくてはならないのですが、一般的に多くの病気を個人的レベルにあてはめてみると次のような事が分っていません。
①治療を行うことにより、病気が就労可能な状態まで改善されているかどうか。
②病気の進行が、労働者の社会生活や就労を困難にする程度になるまで、どのくらいの期間がかかるのか。
③障害を残さないで就労可能な状態になるまで治癒するのか。
これらの事がある程度究明されていないと、休業措置や就労復帰の予測や判断の際に、一律にはいかない状況にあります。
病気の予防は、発病に関与する要因が多数あっても、主な要因がある程度分かっていればばく露させない事が可能です。
しかし、例えば、「たばこの喫煙」と「肺がん」の発生の関連は明らかになっていますが、「喫煙していない人」も肺がんを罹患するので、人体に影響を及ぼす要因と人体影響を明らかにすることは難しいのです。
また、「メンタルヘルス関係」の就労支援、特に「職場復帰」については、専門医を受診し主治医が職場復帰可能と診断されても、産業医も復帰可能とは判断しにくい場合があります。例えば一例として発達障害があり職場不適応となる若い労働者の場合でも、環境要因(出産時の親の年令、合併症などの要因も含む)や、遺伝要因などが絡んで発症しますし、類似の診断名が多く、専門医であっても診断名が一致しない場合や病気の状態が就労中や休業中などの環境要因の変化によっても症候が変動する為、同一の医師であっても診断について病気の経過中に異なる事例があります。
産業医は、職場復帰や就労支援を行う場合、職場の状況や個人的要素などを考慮して、たとえ治療中であっても職場に適応できるか、或いは職場が配慮できるかなどを考え、場合によっては事業主と職場環境の改善の可能性について相談しつつ判断をすることになります。
これらについて職場の同僚や関係者に理解できるよう説明し、了解を得る体制を整える努力をしないと、治療と就労の両立支援やメンタルヘルス不調者の職場復帰を可能にすることは出来ないと思います。
今まで医学では携わってこなかった難しい分野でありますので、不十分ながらも実践しつつ改善し、研究・研鑚をつむことにより目標が達成可能となることを願っています。