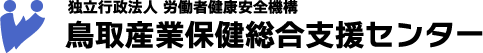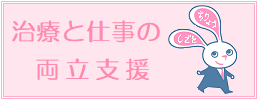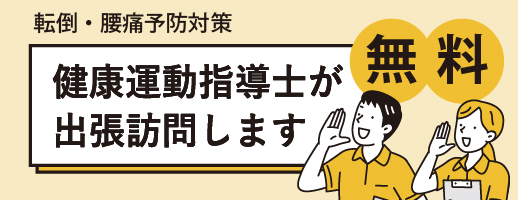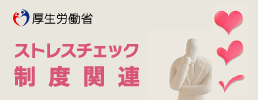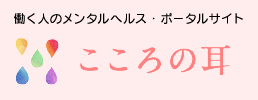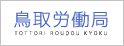鳥取産業保健総合支援センター 所長 黒沢 洋一
世界終末時計
◇世界終末時計は、アメリカ合衆国の雑誌『原子力科学者会報』 の1947年から掲載されているが表紙絵の時計である。核戦争などによる人類の絶滅を『午前0時』とし、その終末までの残り時間を「0時まであと何分」という形で象徴的に示している。2023年1月24日(火)(米国時間),2023年の終末時計が発表された。原子力科学者会報では終末までの残り時間を「1分40秒」から「1分30秒」に改められた。過去76年間で最も破滅に近づいたことになる。最近の世界終末時計では、核問題だけでなく地球温暖化などの地球環境破壊も加味されているようだ。
◇1949年ソビエト連邦が核実験に成功し、核兵器の開発競争が始まったことで世界終末時計は3分前となり、1953年アメリカ合衆国とソ連が水爆実験に成功したときに世界終末時計は2分前と一気に時間は進んだ。1953年の水爆実験は社会に衝撃を与えたようで、水爆実験で蘇った怪獣がニューヨークの街を破壊していくという特撮怪獣映画『原子怪獣現わる』がアメリカで公開され、日本では放射線を吐き散らしてあらゆるものを破壊する『ゴジラ』が公開され大ヒットした。怪獣ゴジラは人間にとっての恐怖の対象、「核の落とし子」として描かれた。このような核問題を扱った映画が次々と制作・公開されヒットした。
◇私が記憶しているのは猿が支配する惑星が実は核戦争後の地球だったいう衝撃的なラストシーンで有名な「猿の惑星」(1968年)である。中学1年生の時、友達といっしょに観に行った。精密な猿のメイキャップが話題となったSF娯楽大作で、十分に楽しめた。劇中の知的な研究職(人間の研究をしているらしい)のメス猿が「私たちにくらべて人間は野蛮で、知能が低いのよ。」と語っている場面は今も鮮明に記憶している。
◇世界終末時計が最も戻ったのは1991年、米ソが第一次戦略兵器削減条約(START1 Strategic Arms Reduction Talks)に調印した時で、17分前まで戻ったようだ。残念ながら、その後時計は進みつつけている。現在、ウクライナ侵攻を背景にロシアと米国との新STARTは停止状態となっており、残り時間は「1分30秒」となった。
鳥取産業保健総合支援センター 所長 黒沢 洋一
どうなる新型コロナ感染症
昨年の夏ごろ、新型コロナ感染症について意見を求められると、「このパンデミックの将来を予測できると言う人は、自信過剰か嘘つきです。専門家は、また南半球のオーストラリアでの動向を注意深く見守っています。オーストラリアは、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの季節流行が復活し、病院が圧迫されています。」という海外の権威ある医学雑誌の記事を引用していました。新型コロナウイルス感染症は3年目を向かえてそろそろ終息という楽観論に根拠はなく、予想不能であり、冬季のインフルエンザとの同時流行に備える必要があるという趣旨です。
振り返ると、第7波に第8波とつづき感染者が急拡大しました。重症化の割合は初期の感染に比較して高くないものの、感染者数が極めて多いため一日の新型コロナ感染症に関連する死亡者数が過去最大となる日が続きました。インフルエンザとの同時流行もみられました。
わが国で新型コロナ感染症が確認されてからまる3年が過ぎた2023年1月、感染症対策において大きな動きがありました。新型コロナの感染症法上の位置づけについて、政府は1月27日の対策本部で、大型連休明けの5月8日に、今の「2類相当」から、季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に移行する方針を決定しました。
医療費などの公費負担については段階的に縮小し、3月上旬をめどに医療体制とあわせ具体的な方針を示すとしています。マスクについては、屋内、屋外を問わず、着用を個人の判断に委ねることを基本にするよう見直すとした上で、具体的な見直し時期を検討していく考えを示しました。
このほか、スポーツやコンサートのイベントでは引き続きマスクの着用を求める一方で、応援などのために大声を出すことを認めました。今後、各都道府県がこれらの方針に基づいてガイドラインの見直しを行うようです。岸田総理大臣が「ウィズコロナの取り組みをさらに進め、あらゆる場面で日常を取り戻すことができるよう着実に歩みを進めていく」と述べたように、通常の生活に向けて本格的に動き出すということでしょう。
今後、国の方針をもとに、各事業所でも新型コロナ感染への対応が検討されることになるでしょうが、その際、産業医に意見を求められる機会が多くなると予測されます。新型コロナの感染症法上の位置づけの見直しの方針はよいと思いますが、絶えず準備せよという意味で、私はアメリカで新型についてコロナの感染対策を主導してきたファウチ博士の言葉を引用しようかと考えています。「私たちはまだパンデミックのまっただ中にいる。」(ファウチ博士NHKの単独インタビューに応じて)。
鳥取産業保健総合支援センター 所長 黒沢 洋一
人口減少と物価上昇
カタールで開催されたサッカーワールドカップの余韻が冷めやらぬ12月中旬、日本銀行(日銀)の長期金利の変動許容幅を従来の0.25%から0.5%に拡大するというニュースに注目が集まった。デフレ脱却(賃金の上昇を伴った安定的な物価上昇)と持続的な経済成長を目指して超低金利政策を続けてきた日銀の方針転換ではないかという憶測が飛び交った。為替は一時急激な円高に振れ、株価は急落した。近年、コロナショックやウクライナ危機などいくつかの要因を背景に、世界の物価は上昇した。超低金利政策がひとつの要因となった過度な円安傾向も加わり、わが国の物価も上昇した。しかし、賃金の上昇を伴わない状況での物価上昇であり、家計への負担が懸念されている。
今回のニュースを聞いて、数年前に書いた医事新報の「少子化と研究」という小品を思い出した。日銀の物価安定の目標である(賃金の上昇を伴う)消費者物価の前年比上昇率2%の目標に対して、「少子高齢化により急激な人口減少が生じているので、物価上昇は難しいのではないかと思う。」と書いた。少子化対策が重要課題であることを強調するために、当時アベノミクスで話題となっていた日銀の目標を取り上げたのだ。ただし、急激な人口減少下で物価上昇は難しいのではないかと思うのは門外漢の直感で、根拠があるわけではなかった。気になったので、最近の議論をインターネット上で調べてみると、人口減少国でも物価は上昇する(賃金上昇にはふれていない)、デフレは人口減少が原因ではないなどの反対意見も出され、以前より活発に議論されているようだ。フランスの歴史学者エマニュエル・ドットに代表される人口統計に着目した方法論が注目されていることもあり、賃金、物価と人口統計に関係する研究を一層進めてほしいと思った次第である。
鳥取産業保健総合支援センター 所長 黒沢 洋一
COP27
ごく最近、11月なのに太陽の日差しが夏ように強く感じられることがあった。11月がこんなに暖かかったという記憶があまりない。大丈夫かなと思ってしまう。
産業革命以降増え続ける大気中の二酸化炭素には地表からの熱の放散を妨げて地表を暖める働き「温室効果」があり、地球全体の平均気温を上昇させる。気温上昇による海水面の上昇、気候変動、生態系の急激な変化が懸念されている。1997(平成9)年にわが国で開催された第3回「気候変動枠組条約締約国会議」(COP3)は、温室効果ガス排出量の削減目標について法的拘束力、数値目標を定めた「京都議定書」が採択される画期的な会議となった。それから、25年が過ぎたが、先進国と途上国の対立、アメリカ等の大国の一時的離脱などがあり、その歩みは順調ではないようだ。
先日エジプトで第27回「気候変動枠組条約締約国会議」(COP27)が開催された。地球温暖化がもたらした「損失と被害」を支援する基金の創設で合意したことが今回の会議の大きな成果として取り上げられていた。被害を受けやすい途上国が長年求めていたが、巨額の負担を恐れる先進国が反対してきたようだ。気候危機はすでに顕在化しつつあり、今年、パキスタンでは2カ月に及ぶ猛暑のあと、8月、大洪水が国土の3分の1をのみ込み、3300万人の生活が破壊されたというニュースは衝撃を与えた。確かに温室効果ガスの排出量の少ない途上国が、温室効果ガスによる甚大な被害を受けている。温室効果ガスを大量に排出した先進国がその「損失と被害」を支援すべきという理屈で、途上国の主張が認められたといえよう。一方、先進国が求めた1.5℃以下におさえるという目標は棚上げになったようだ。背景にエネルギー危機があり、議論は進まなかったようだ。
今後のCOPの動向に注目したい。
鳥取産業保健総合支援センター 所長 黒沢 洋一
エイジフレンドリー
エイジフレンドリーは、世界保健機関(WHO)が提唱している「高齢者の特性を考慮した」考え方で、労働者の高齢化がすすむわが国の職場の健康管理では重要な課題となっています。高年齢労働者の雇用者数は過去10年で約1.5倍に増加し、雇用者全体に占める60歳以上の高齢者の割合は17.8%を占め、1千万人近い高年齢労働者がわが国の産業を支えています。体力・持久力、視覚・聴力等の身体機能は加齢による影響を受けますが、経験に基づく技術や判断力は加齢により向上します。その特性により高年齢労働者は、貴重な労働力となっています。一方、休業4日以上の死傷者数に占める60歳以上の高齢者の割合は高く、高年齢労働者の労働災害は重症化しやすいことが分かっています。そのため、高齢者が能力を発揮し、安心して活躍できるようにするための「エイジフレンドリーガイドライン」(厚労省 2020年)が取りまとめられました。求められる事項として、
(1)安全衛生管理体制の確立等
(2)職場環境の改善
(3)高年齢労働者の健康や体力の状況の把握
(4)高年齢労働者の健康状態や体力に応じた対応
(5)安全衛生教育の実施
が挙げられています。職場環境の改善では、転倒防止が重要ポイントで、段差の解消、手すりの設置、床のすべり止め、照度の確保などが推奨されています。「エイジフレンドリーガイドライン」は、貴重な労働力を守る予防活動指針ですので、ぜひ活用してください。