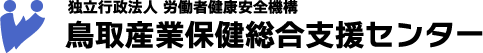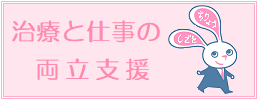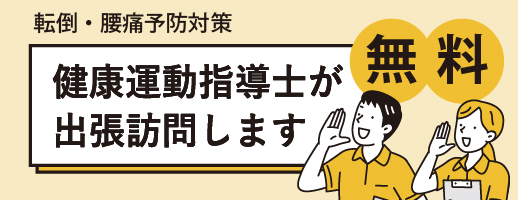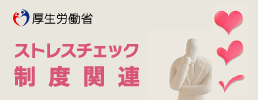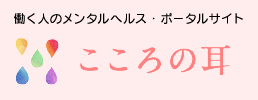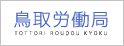鳥取産業保健総合支援センター 所長 能勢 隆之
働き方改革が2019年4月1日に施行され、各事業場はその主旨に合わせて改革を進めてきましたが、最近では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためやデジタル技術の普及によってテレワークなど新しい労働形態が導入されるようになりました。これまでは、日中に会社に出社し、1日8時間労働をすることを基本とし、必要に応じて夜勤労働、深夜労働などを行ったり、変形労働時間制や裁量労働制などを採用しながら働いた労働時間に応じた労務管理を行ってきました。
働き方改革では、労働者の健康を保持・増進するため、オーバーワークとならないよう8時間以上働く労働者の労働時間に上限規制を導入し、原則として月45時間、年360時間までの時間超過を限度としました。先の「1月によせて」において、睡眠時間は少なくとも1日6時間以上とることが必要であると述べましたが、労働者の健康な生活を維持するためには、睡眠のみでなく勤務時間インターバルも十分にとることが必要であり、時間外労働の上限規制はこの勤務時間インターバルを確保するためにも必要なものです。海外では社会主義市場経済体制をとる国もあり、働き方も多様化すると思いますが、日本は今日まで資本主義経済体制をとっており、過去には頑張って働く(長時間人よりも多く労働する)ことが美徳とされ、収入を多く得た者が勝者となり、その結果経済格差がうまれてきました。
また働き方改革の重点として、休まず働くのではなく有給休暇を確実にとり、休養することを進めています。今まで有給休暇を取得してこなかった労働者にも最低5日は強制的に取得させるよう事業主に求め、労働者がリフレッシュできることを期待しています。また改革では、非正規雇用労働者(低賃金労働者)の割合が増加しているので正規労働者と不合理な待遇格差がおこることを防止し、労働条件を良好に維持することも目指しています。
最近のデジタル化の発展は業務の効率化やコスト削減を推進し、会社においては、出勤することなく自宅などでのリモートワークが採用されるようになり、労務管理が困難になってきています。働き方改革は従来の労働形態を基本に策定したものであるので、デジタル化には充分な対応となっていない部分があります。再度、現状に合った労務管理のあり方を検討することが必要になっていると考えます。
鳥取産業保健総合支援センター 所長 能勢 隆之
新年明けましておめでとうございます。
今年も平穏に仕事を続けるため、まずは健康づくりに努め、健康を維持し、増進することに努めましょう。健康づくりのキャンペーンには「運動・栄養・休養」が3種の神器のように唱えられています。運動と栄養については多くとりあげられており、休養については気分転換やレクレーションをすることが提案されますが、最も重要な睡眠をとることについては言及されることが多くありません。色々な要因で睡眠が十分にとれない人が多くあります。不眠のリスク要因として労働状況たとえば長時間労働、深夜労働などによる睡眠時間不足がとりあげられます。睡眠が上手にとれず、不眠症、うつ病、そして生活習慣病などに罹患する労働者もたくさんあります。
今回は睡眠障害について解説します。睡眠障害には次の4つのタイプがあります。①入眠障害(寝つきが悪い)、②中途覚醒(眠りが浅く、途中で何回も目が覚める。中途覚醒時間も10年毎に10分ずつ増加するといわれています。)、③早朝覚醒(就寝する時間にもよりますが午前2~3時の早朝に目が覚めてしまう)、④熟眠障害(深い睡眠は年齢とともに減少することなどにより、ある程度眠ってもぐっすり眠れたという満足感が得られない)などです。
これらの睡眠障害により十分な休息がとれず、倦怠感がとれないだけでなく意欲低下、集中力低下、抑うつ感、頭重、めまい、食欲不振などさまざまな症状があらわれ、仕事の能率が低下します。また、これからは再雇用などで高年齢労働者が増加することが予測されており、加齢とともに睡眠の量と質は低下するので、不十分な睡眠をとりもどすための土日の「寝だめ」では解消できない労働者が増加します。
さらに働き方が多様化し、長時間労働者(最低6時間の睡眠時間のとれない超過勤務をしている者)、交替勤務者(日勤・夜勤を交替で勤務し、概日リズムが乱れる勤務をしている者)、勤務間インターバルの短い労働者(勤務間インターバルが11時間以下の勤務者は6時間睡眠をとっていない)が増加しており、改善する必要があります。
そのためには事業場での睡眠保健教育をすることが重要です。一般的な健康教育の内容として、①毎日同じ時間に起床し、朝の光を浴びるなど生体時計のリズムを整える、②アルコール、タバコ、カフェインを含む飲料などは脳の覚醒が3~4時間つづくので寝る前には控える、③眠る30分~1時間前に入浴する(40℃のぬるま湯につかると深い眠りをとることができる)などを中心に労働者が実践しやすいものをとりあげて行うのが良いと思います。
今年も健康で安全な就労生活を送りましょう。
鳥取産業保健総合支援センター 所長 能勢 隆之
新型コロナウイルス感染症の流行は、第6波の可能性が懸念されています(令和3年11月末現在)。新型コロナウイルスは、SARSのようにコロナウイルス株の変異などウイルス自体の原因によって感染力が変化することが推測され、第6波とともに感染流行が変異によって影響を受ける可能性もあります。しかしウイルスの感染形態が変化しても感染がなくなるわけではなく、今までのウイルス感染症(たとえばインフルエンザなど)と同様に流行を繰り返し発生し、いわゆる「ウイズコロナ時代」に移行していくことが予測されます。事業場としてはウイズコロナ時代に適した人材の確保や生産体制の再構築などの整備が急がれます。
ウイズコロナ状況下での企業継続計画(BCP)の推進のためには、産業保健として行われていた事業所内の感染症対策は今までとは異なる新しい展開を検討しなくてはなりません。今までのように産業保健スタッフが労働者の安全と健康の確保のみに注目していたのでは、経営の合理化などを重視する経営者側と目的観が異なり、トラブルが起こることが予測されます。改正労働安全衛生法では、労働者の長時間労働の抑制、また過労死や職場不適応によるメンタルヘルス不調、自殺などの発生を防止するため、産業医・産業保健職務の権限拡大やその職務内容が明示されました。コロナ禍で経営不振に陥ったことを改善するため、事業所では人員の解雇や経営の縮小を優先する取り組みが行われてきました。コロナ禍で「働き方改革」や労働者の健康保持・増進といった組織の健全性を高める「健康経営」の理念が軽視されがちなことが心配されます。
日本型の企業経営は終身雇用制、年功序列、企業内組合(労使協調主義)を3種の神器として行われてきました。これは良いところもありますが、稟議・集団主義・平等主義・現場主義・隠蔽などが重視され、労働者個人の健全性がややもすると無視され、緊急対応のためには労働強化もやむを得ないという企業体質が優先されることも考えられます。これらにより労働環境が悪化して健康障害やメンタルヘルス不調が発生しやすくなりますので、そのような状況を回避するため、働き方改革の推進に努めなければなりません。産業保健スタッフは、今回の新型コロナウイルス感染症の流行を教訓として、感染症が企業に発生したあるいは発生するおそれがある場合を想定した企業内危機管理の対処方法を具体的に検討しておくことが必要です。まず労働者の安全・健康確保を図りつつ、産業保健分野のスタッフも積極的に企業のBCPに参加する考えと十分な知識を醸成しておくことが重要です。
鳥取産業保健総合支援センター 所長 能勢 隆之
今回のコロナウイルス感染症のパンデミック(世界的流行)を終息させるため、ロックダウンや入国制限など種々の対策が世界の各国で実施されました。その対策の一つに予防接種が先進国を中心に国家的事業として行われました。今までのパンデミックで、このような地球的規模での感染症対策は行われたことはありません。日本においても緊急事態宣言を発するとともに、対策の一つに予防接種(外国産のコロナワクチン接種)が実施されました。
産業保健の事業の一つに職場での感染症対策があります。職場の感染症対策の内容に、職場で予防接種を労働者に実施する場合がありますが、法令上の規定はありません。事業場内で特定の感染症がまん延するおそれがある場合、特に業務に関連して感染症にかかるおそれがある場合は予防接種を考える必要があります。この際の予防接種は事業主の責任において実施されるものであり、接種を実施する産業医又は他の医療職は事業主との契約に基づいて接種を行うことになりますが、接種による副作用や禁忌について十分な問診、健康状態の確認をした上で実施するものです。
事業場での予防接種は、個体(労働者)が獲得した免疫によって職場内での集団発生を抑制し、事業の継続性(BCP)を確保することが目標になります。感染症の流行期間など流行状況にもよりますが、集団発生を抑制するためには、ワクチン接種による免疫効果が少なくとも半年以上継続することが必要です。今回のmRNAワクチンは、ウイルス遺伝子のうち免疫原性(抗原)を意味する遺伝子の塩基配列を基にヒトの細胞が利用できる形にしたものです。それをヒトの筋肉細胞に接種することで、免疫細胞が認識(錯覚)して抗体をつくることにより獲得免疫を成立させるようにしたものです。開発段階で免疫効果の追跡期間が3カ月から6カ月間といわれていますので長期の効果は未確定です。そのため、接種後、接種者の抗体価を測定し、抗体価が低下していれば追加してワクチンを接種しなければ感染の抑制にはなりません。集団免疫体制がつくりにくいので感染予防のためには、ワクチン接種だけに頼ることなく、今までのように感染予防としてマスクの着用、ウイルスに負けない体力の維持、3密を避けるなど種々の環境要因を維持することが大切です。事業場内での感染症予防のための予防接種の実施については、安全衛生委員会の適切な検討により対応されるのが適当と思います。
鳥取産業保健総合支援センター 所長 能勢 隆之
人生100年時代に向けて高年齢労働者が安心、安全そして健康に働ける職場環境づくりや、労働災害防止を目ざして「60歳以上の高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(エイジフレンドリーガイドライン)」が公表されています。
具体的対策として、従来の「身体機能低下を補う設備、装置の導入」、「健康や体力の状況を日常的に把握する」、「高齢者の特性に注目した安全衛生教育」に加えて、今最も注目されている「新型コロナウイルス感染症予防」が追加されています。
これらは主として高年齢労働者を事業場に受け入れて、若い労働者と一緒に作業をスムーズに行うための対策を考えています。高年齢労働者が作業を遂行するためには、本人もそうですが、周囲の労働者が高年齢労働者の身体的特性に合わせて対応することや、それ以上に精神的特性を理解し、受け入れ、配慮しながら協同して働くことも重要であるからです。
高年齢労働者の早老の特性(初老期認知症といわれることもある)として、反応が遅くなる、複雑な組合せと判断をしながらの作業は不得意であることや、特に精神機能は軽度認知症が伴うので新しい作業の記憶が難しく、そのために予期せぬミスをくりかえすことなどが考えられます。
高年齢労働者の精神反応の特性としては気が短くなり、ささいなことに強く反応して攻撃的になりやすくなってきます。このことを本人も職場の同僚や上司も気がつかないまま大きなトラブルとなり、仕事に支障をきたすおそれがあります。高年齢労働者を受け入れることは、事業主や若い労働者に新しい視点を取り入れた対応を求めています。
企業の「働き方改革」においても、現役時代の労働環境のみに注目するのではなく、定年退職後の高年齢での再雇用労働者の受け入れも視野に入れた職場環境改善の検討が必要です。高年齢労働者の精神機能の低下に注目した新しい産業保健の研究と対策がポストコロナに一層発展することを期待します。